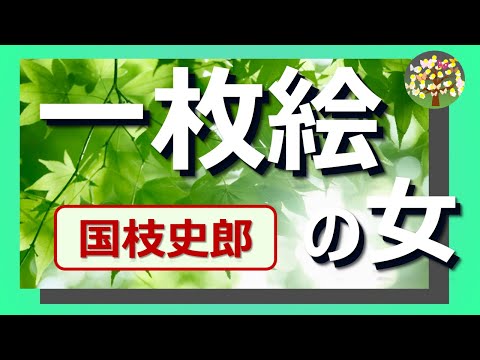動画要約まとめ
- ・ 国枝史郎の短編小説「一枚絵の女」
- ・ 【国枝史郎】(1887年–1943年)
- ・ 怪奇・幻想・耽美的な伝奇小説の書き手ですが、他に探偵小説、戯曲なども執筆しています。長野県茅野市出身。
- ・ 【作品中に出てくる浮世絵師】
- ・ 喜多川歌麿(きたがわうたまろ)《1753年-1806年》
- ・ 江戸時代に活躍した浮世絵師。背景を省略して白雲母を散りばめ、更にそれまで全身が描かれていた美人画の体を省いて、顔を中心とする構図を考案したと云われています。これにより、美人画に表情だけでなく内面や艶も詳細に描かれます。
- ・ 鈴木春信(すずきはるのぶ)《1725年?-1770年》
- ・ 江戸時代中期の浮世絵師。細身で可憐、繊細な表情の美人画で人気を博し、浮世絵というとまず思い浮かべる木版多色摺りの錦絵誕生に決定的な役割を果たし、後の浮世絵の発展に多大な影響を及ぼしました。
- ・ 鳥文斎栄之(ちょうぶんさいえいし)または細田栄之(ほそだえいし[4])《1756年-1829年》
- ・ 江戸時代後期の浮世絵師、旗本(細田氏)。寛政から文化文政期にかけて活躍しました。絵は初め狩野典信に学び、師の号「栄川院」より「栄」の一字を譲り受け栄之と号しましたが、後に浮世絵に転じたため、師の栄川院より破門を言い渡されました。しかし、栄之の号だけは永く使用しました。将軍徳川家治の小納戸役に列し絵の具方を務め、家治が絵を好んだので御意に叶い、日々お側にいて「御絵のとも役を」承っていました。《1781年~1783年》
- ・ 初代歌川豊国(しょだいうたがわとよくに)《1769年-1825年》
- ・ 江戸時代の浮世絵師。幼少期に歌川派の創始者歌川豊春の元で学び歌川豊国と称し、理想の美しさを表現した役者絵や美人画で絶大な人気を得ました。歌川派の中興の祖となった豊国は多数の弟子たちを抱え、門人が代々「豊国」を襲名しました。
- ・ 文中「悪因悪果」の読みを間違えました、正しくは「あくいんあっか」でした。申し訳ありませんでした。
- ・ #朗読#国枝史郎#一枚絵の女
YouTube - 動画概要欄 -
国枝史郎の短編小説「一枚絵の女」
【国枝史郎】(1887年– 1943年)
怪奇・幻想・耽美的な伝奇小説の書き手ですが、他に探偵小説、戯曲なども執筆しています。長野県茅野市出身。
【作品中に出てくる浮世絵師】
喜多川 歌麿(きたがわ うたまろ)《1753年 - 1806年》
江戸時代に活躍した浮世絵師。背景を省略して白雲母を散りばめ、更にそれまで全身が描かれていた美人画の体を省いて、顔を中心とする構図を考案したと云われています。これにより、美人画に表情だけでなく内面や艶も詳細に描かれます。
鈴木春信(すずき はるのぶ)《1725年?-1770年》
江戸時代中期の浮世絵師。細身で可憐、繊細な表情の美人画で人気を博し、浮世絵というとまず思い浮かべる木版多色摺りの錦絵誕生に決定的な役割を果たし、後の浮世絵の発展に多大な影響を及ぼしました。
鳥文斎 栄之(ちょうぶんさい えいし)または細田栄之(ほそだ えいし[4])《1756年-1829年》
江戸時代後期の浮世絵師、旗本(細田氏)。寛政から文化文政期にかけて活躍しました。絵は初め狩野典信に学び、師の号「栄川院」より「栄」の一字を譲り受け栄之と号しましたが、後に浮世絵に転じたため、師の栄川院より破門を言い渡されました。しかし、栄之の号だけは永く使用しました。将軍徳川家治の小納戸役に列し絵の具方を務め、家治が絵を好んだので御意に叶い、日々お側にいて「御絵のとも役を」承っていました。《1781年~1783年》
初代 歌川豊国(しょだい うたがわ とよくに)《1769年- 1825年》
江戸時代の浮世絵師。幼少期に歌川派の創始者歌川豊春の元で学び歌川豊国と称し、理想の美しさを表現した役者絵や美人画で絶大な人気を得ました。歌川派の中興の祖となった豊国は多数の弟子たちを抱え、門人が代々「豊国」を襲名しました。
文中「悪因悪果」の読みを間違えました、正しくは「あくいんあっか」でした。申し訳ありませんでした。
#朗読 #国枝史郎 #一枚絵の女
朗読系ちゃんねる
怖い話 怪談 朗読
音本倶楽部 朗読部 Harugoro Shichimi
夜咄頼麦 / ねむり屋
ほがら朗読堂
【怖い話】りっきぃの夜話
西村俊彦の朗読ノオト
ゲーデルの不完全ラジオ
ごまだんごの怪奇なチャンネル
MMC SUKOYAKA
山本周五郎チャンネル
怪談朗読 低音ボイス【びびっとな】
【公式】窪田等の世界
あべよしみ 朗読の部屋
mamezoの朗読
海渡みなみの朗読アラモード
シャボン 朗読横丁
【公式】名作朗読チャンネル Bun-Gei
ベルエポックの朗読チャンネル
フリーアナウンサーしまえりこの朗読読み聞かせ
Ted Hidaka - Voice Narrations and Readings | 日髙徹郎
語り屋デリバリー
夜魔猫亭綺譚
ぐっすりおやすみチャンネル
今宮 まほろ
癒しの睡眠用朗読チャンネル
【公式】窪田等の世界
怪談夜話
朗読の時間
眠れる朗読
奇妙な物語朗読ch豚ゴリラ
キテレツラヂオ
朗読『耽溺と諧謔の昭和』
舌たらずの朗読屋
聴くだけでも面白い話ch